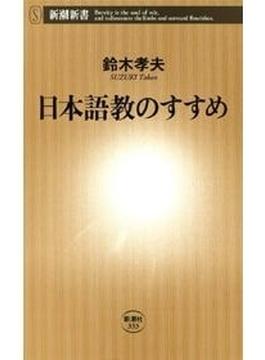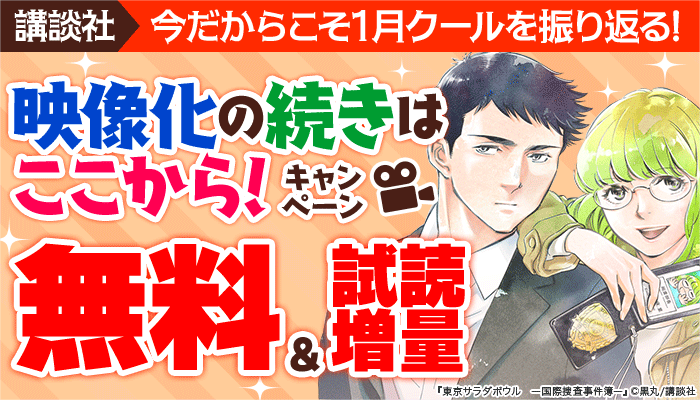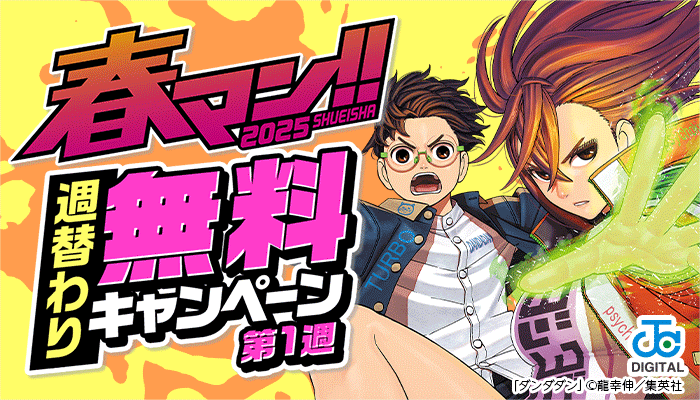中高生~大学生にはお薦め
2009/12/12 23:09
9人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:yukkiebeer - この投稿者のレビュー一覧を見る
私は学生時代から四半世紀間、この著者の社会言語学の本を愛読してきました。
本書「日本語教のすすめ」は平成19年から3年間「新潮45」に連載した文章を加筆修正したものとのこと。著者の著作に縁のない読者も多い雑誌での連載ですから、書かれていることはこれまで著者が主張してきたことの反復であり、私には目新しいものはないものの、外国語と日本語の違いについてなんとなく興味を持ち始めた中学生以上の読者には十分楽しめる一冊だと思います。
著者がまず具体例と共に提示するのは、外国語を学ぶと「この世界にはなんと色々な変わったことを思ったり考えたりする人がいるものかという、人間のものの見方の多様性についての理解が深まる」楽しさです。
日本人は虹が七色だと“知っている”が、ドイツでは五色だと思っている人が多いこと。
太陽を赤く塗るのは日本では常識だが、英語圏では黄色であるのが当たり前であること。
こんな日本語と外国語との通念の差について明快かつ興味深く著者は筆を進めています。
しかしこうした彼我の違いの面白さから説き起こして著者が最終的に強く主張するのは、日本固有の、そして諸外国に対して普遍的に説くべき価値観を日本人が日本語で積極的に発信していくことの重要性です。
著者いわく、日本語に対して不必要な劣等感をもつ日本人は多いのだとか。
しかし日本語は1億以上もの話者を持つ、世界的にも巨大な言語です。
英語をはじめてとして欧州言語に過剰な劣等感を持つのではなく、この日本語を使って発信していくことができるはず。そう著者は説きます。
本書によって目を洗われる読者は間違いなく多いと思います。
*虹の七色を英語で言う場合は、著者が70頁で記す「Richard of York gained battles in vain.」よりも「Richard of York goes battling in vain.」というほうが一般的なようです。
*238頁8行目~239頁2行目の文章と、240頁8行目~241頁2行目の文章がほぼ同一です。推敲が完了していない原稿を印刷して、ゲラ刷りの際に編集者が校閲に失敗した様子です。
投稿元:
レビューを見る
日本語の尊さに、気付いた。やはり「英語」が一番と思うのは、日本人の特有の悲観的な癖なのであろうか(笑)
6000ある言葉のなかでも、1億2000万人が使っている日本語を価値を大切にしたい!
投稿元:
レビューを見る
[ 内容 ]
「日本語は英語に比べて未熟で非論理的な劣等言語である」-こんな自虐的な意見に耳を傾けてはいけない。
われらが母語、日本語は世界に誇る大言語なのだ。
「日本語はテレビ型言語」「人称の本質とは何か」「天狗の鼻を“長い”ではなく“高い”と表現する理由」等々、言語社会学の巨匠が半世紀にわたる研究の成果を惜しげもなく披露。
読むほどに、その知られざる奥深さ、面白さが伝わってくる究極の日本語講座。
[ 目次 ]
第1章 日本語は誤解されている(日本語ってどんな言語 漢字の読みはなぜややこしいのか ラジオ型言語とテレビ型言語)
第2章 言語が違えば文化も変わる(虹にはいくつの色があるのか 太陽は世界のどこでも赤いのか 蛾と鯨が同じ理由 文化によって異なる羞恥心)
第3章 言葉に秘められた奥深い世界(天狗の鼻は「長い」ではなく「高い」 形容詞の中身はなに? 江戸時代、「日本酒」はなかった)
第4章 日本語に人称代名詞は存在しない(身内の呼び方の方程式 日本語の人称代名詞を巡る問題 指示語と自己中心語のしくみ 「人称」の本質は何か)
第5章 日本語に対する考えを改めよう(日本人のもつ相手不在の外国語観 日本語教のすすめ)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
投稿元:
レビューを見る
大学受験時代に「武器としての言葉」を読んで以来、時々手にしてきた著者の本。虹は何色かとかオレンジ色のネコの話とか、またこのネタかと思う部分もないではないですが、新書というフォーマットで新しい若い読者を獲得することも大事なのでしょうね。
投稿元:
レビューを見る
(推薦者コメント)
日本語は本当に非論理的か。日本語を考えるすべての人へ、鈴木孝夫からのメッセージ。
投稿元:
レビューを見る
言語社会学者、鈴木孝雄の書。
世界には6千もの言語があるとのこと。
日本語を他国の言語と比較し、その独自性を追求していくなかで、日本語の素晴らしさを説かれている。
当たり前のように接し、当たり前のように使用している母国語の日本語。だからこそ、気付かないその魅力を十二分に解説されている。
二重音声、色、人称の話は感心しながら楽しく読めた。
また、文明と言語の絡み合いについて力説されている当たりは、後段の日本語教のすすめに説得力を与えている。
日本語が、世界から、そして日本人自身から過小に評価されている点について、それを大きく撥ね除けるように日本語の魅力が綴られている。
著者は新興宗教を起こしたとのこと。
それが、本書のタイトルにある「日本語教」。冗談だと思うが、内容はいたってまじめで、曰く『この世に折角生を享(う)けながら、日本語と言う素晴らしい言語を知らずに空しく死んでいく人を、一人でも少なくする努力をしよう』とのこと。
本当に面白い本で著者の他の本にも当たってみたくなった。
----------------
【目次】
第1章 日本語は誤解されている(日本語ってどんな言語 漢字の読みはなぜややこしいのか ラジオ型言語とテレビ型言語)
第2章 言語が違えば文化も変わる(虹にはいくつの色があるのか 太陽は世界のどこでも赤いのか 蛾と鯨が同じ理由 文化によって異なる羞恥心)
第3章 言葉に秘められた奥深い世界(天狗の鼻は「長い」ではなく「高い」 形容詞の中身はなに? 江戸時代、「日本酒」はなかった)
第4章 日本語に人称代名詞は存在しない(身内の呼び方の方程式 日本語の人称代名詞を巡る問題 指示語と自己中心語のしくみ 「人称」の本質は何か)
第5章 日本語に対する考えを改めよう(日本人のもつ相手不在の外国語観 日本語教のすすめ)
----------------
【内容(「BOOK」データベースより)】
「日本語は英語に比べて未熟で非論理的な劣等言語である」―こんな自虐的な意見に耳を傾けてはいけない。われらが母語、日本語は世界に誇る大言語なのだ。「日本語はテレビ型言語」「人称の本質とは何か」「天狗の鼻を“長い”ではなく“高い”と表現する理由」等々、言語社会学の巨匠が半世紀にわたる研究の成果を惜しげもなく披露。読むほどに、その知られざる奥深さ、面白さが伝わってくる究極の日本語講座。
----------------
投稿元:
レビューを見る
「言葉を使って他人をこちらが望むように動かすこと、これを言語学では言語のもつ他動機能(conative function)と呼びますが、日本人の言語行動にはこの言葉の使い方がどうも弱いように私は思います。」p215
投稿元:
レビューを見る
鈴木孝夫さんのこれまでの研究内容、持論がわかりやすく凝縮された一冊。日本、日本語の素晴らしさの世界への発信という著者の希望は、不十分ながら近年急ピッチで進んでいる気がする。少子化で外国人労働者を多く迎え入れたり、観光業に力を入れたりする中で、不可欠だと日本社会が思い始めたのか。その対象が日本のアニメやエンタメ部分ばかりなのは、鈴木さんの意図するところではないかもしれないし、相変わらず日本の英語へのコンプレックスは凄いけれど(私もそのひとりか)、。
また鈴木さんが研究対象そのものでなく、広く好奇心を持って積極的な行動力を持っていたことが、これだけのインパクトの大きな業績に繋がっていると思った。目の付け所と対象の絞り方が凄い。当たり前と思われていることに改めて疑問を持ち、分析、発展していくことはどの分野でも大事なのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
日本語の国際普及は、文化侵略でも帝国主義でもなく、世界へのお返しである
卑下するのではなく、普及を意識した活動や行動をすべし、だね
投稿元:
レビューを見る
言語学の“3K”は、やらない――とおっしゃる言語社会学者、
鈴木孝夫先生の日本語称揚集成。
「言語学の3K」とは、
敬語(の研究),系統論,漢字の起源解釈の三つを指すのだそうだ【*1】。
本書は『新潮45』で2007-2009年に18回に渡って連載された「日本語万華鏡」の
加筆修正版で、新しい表題は最終回のタイトル。
個人的には「日本語万華鏡」のままの方がよかったような気もするけど、
ともかく、最近になって改めて読み直したくなったので購入。
日本語独特の曖昧さ、ややこしさと、その理由について、
また、欧米の言語との違いについて、
一般人が自明のこととして普段深く考えずにいる問題に光を当て、
わかりやすく解説。
日本語は日本国内でしか用いられないマイナー言語だと考えられているが、
使用者である日本人は一億人以上存在するのだから、立派な「大言語」なのだし、
政治経済における国際的な交渉力を底上げするためにも、
日本語および日本文化を積極的に海外へ発信すべきである――とのこと。
最近は、漫画やアニメを通して日本に興味を持ち、
日本語を理解したいと考える諸外国の人が増えている様子が、
盛んにメディアで取り上げられていて、
少しずつ、いい方向へ向かっているようだけれども、
相変わらず政治の場では今一つ、二つ、といったところだろうか。
しかし、連載中同様、
不意に遠藤ミチロウの名が出てきたところ【*2】で笑ってしまった。
【*1】『新潮45』2007年5月号「ビートたけしの達人対談」より。
【*2】『新潮45』2008年1月号,本書ではp.163。
投稿元:
レビューを見る
外国人に日本語を勉強してもらうことに非常に共感を覚えた。
日本の文化である日本語をどんどん発信して、外国人に日本後を覚えてもらい、移住して働いてもらうことも日本の未来にとっては重要なんじゃなのかなとこの本を読んで思った。
投稿元:
レビューを見る
音読み 訓読み
漢字からなる専門用語は理解しやすい
猿人、pithecanthrope apeのギリシャ語、後半がmanを表すギリシャ語
英米は新聞や雑誌など少数のインテリを念頭においた高級紙と、一般大衆向けとはっきり分かれている
日本は国民全てを対象とする一般紙がある。
日本語が社会の上下を区別する必要のない言語だから
何度かアメリカの大学で日本語を教えた経験から気づいたことは、学生たちの学習態度がとても攻撃的だということでした。自分たちが理解できないことがあると、外国にはこういう考え方もあるのかとか、あるいはこの点はアメリカ人も見習ったほうがいいのではといった、自分たちの在り方を反省する態度はほとんどみららず、すぐ日本批判すなわち相手攻撃にでるのです。
中国の外国語教育の重点は、中国のよさ、中国人に考え方を外国に広め外国人に知らせて、相手を畏怖させるという自国のよさの対外宣伝、外国人の啓蒙に置かれていた
投稿元:
レビューを見る
文学部と医学部を卒業した上で、経済学や地球環境にも精通してバランスの良い主張が人気の慶応大・名誉教授の鈴木センセイの本。世界中に広がる英語が幅を利かす「英語帝国主義」のもたらす問題点を批判し、極東の一島国だけで話されている日本語を「世界に誇る大言語」と絶賛し、その素晴らしさを解説する。日本で7色とされている虹は英米では6色・ドイツでは5色という「文化と言語」の関係を示したエピソードや、漢字に音訓の両読みがある理由、自らが「日本語教」なる新興宗教(?)を立ち上げた背景など、楽しく読める「鈴木ワールド」入門書とも呼ぶべき本。
投稿元:
レビューを見る
日本語の構造について分析した一冊。
日本語について外国語との比較が非常に面白かった。
またタイトルの通り、日本語に対しての愛情と情熱があふれてた。
投稿元:
レビューを見る
第4章「日本語に人称代名詞は存在しない」については、家族の中で使われる「父」「姉」など卑近な例を用いて、日本語での指示代名詞について説得力のある興味深い説明がされていて面白い。
また、著者は海外における外国語学習の位置付けが、例えばライバル国の事情をいち早く把握して出し抜くことであったり(米国)、自国の歴史を他国に宣伝することであったり(中国)して、普段考えているより多様な目的が存在しているということを知れたのは面白かった。
一方で、著者の過ごしてきた年代を考慮すると仕方がないことのようにも思えるが、国民と民族を同一視する表現や、いわゆる「若者」に対してのステレオティピックな思いが表されているのはすこし気になった。
また、著者は英語学習強化よりもむしろ、日本語教育施策を積極的に展開することで日本の国力増大を図ろうという、「日本語教」の立場を取る。しかし、個人的には、主にフィージビリティの観点から、世界の主要国(しかも主要国の意味するところも今後数十年でまた変わっていく)のすべてに日本語教育を行き渡らせることと、実質的な国際共通語になった英語を習うことなら、明らかに後者の方がコスパが良いと考える。つまり、私は「日本語教」には入信できそうにない。
「日本語教」の信者にはなれそうにないが、日本語の響きや表現、日本語で書かれた詩や歌詞などはとても好きなので、「日本語愛好者」くらいで生きていきたいと思った。